
司会:今日は先日シドニーで行われた日本語教育国際研究大会、ICJLEで現地にいらした先生方に集まっていただき、ご自身の発表を含め、大会ご参加の感想をお伺いしてみようという企画です。伊東先生、伊集院先生、どうぞよろしくお願いします。
伊東・伊集院:よろしくお願いします。
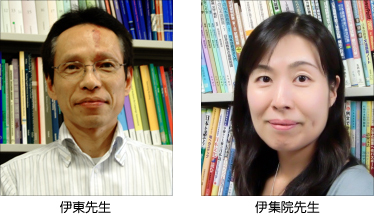
司会:早速ですが、先生方のご感想を伺いたいのですが、今日お越しになれなかった小林幸江先生から、コメントをいただきましたので、読み上げますね。
DLA科研チームは大会3日目にパネル発表を行いました。DLAは、Dialogic Language Assessmentの略で、年少者の言語能力評価を目的として開発したものです。今回は、その柱となる「JSL評価参照枠」の現状の課題と今後の展望について発表しました。豪州の継承語研究者をはじめいろいろ貴重なご意見・ご指摘をいただくことができ、有意義な大会となりました。
ということなんですが、同じチームに所属されている伊東先生、いかがでしたか?
伊東:そうですね、ほんとうに有意義でした。なかなか普段お話しできない人にも来ていただけましたので。佐藤先生(基調講演をなさったプリンストン大学の佐藤慎司先生)もおっしゃっていましたが、継承語は熱いですねー。
司会:何か印象に残った発表などはありましたか。
伊東:ニュージーランドの日本語教育に関する発表を聞きに行きました。REXプログラム(日本の公立学校の教員を海外の日本語教育を行う初等中等教育機関に派遣する文部科学省のプログラム)でJLCに来て研修を受けた先生のご発表でした。ニュージーランドでは日本語学習者が減少しつつあるらしく、その大変な様子もわかって有意義でした。今後どうしていくかがますます重要になってくると率直に思いました。
伊集院:私は石澤先生(司会)や谷口(龍子)先生、本学の院生の発表なども聞けました。普段同じ大学にいてもお互いの研究の話を聞く機会が十分にもてないので、貴重な時間となりました。
司会:私は「分野間のアーティキュレーション」というトピックで行ったインタビューの結果を共同で発表したのですが、日本国内の大学や専門学校の先生から同じような問題を抱えているというコメントをいただけて、今後の方向性も少し見えたかなというところです。
伊東:ちょうどJ-GAP(日本語教育アーティキュレーション・プロジェクト:Japanese Global Articulation Project )のパネルと発表の間でしたよね?
司会:そうでした。実は私J-GAPのパネルが自分の発表の前だって直前まで知らなくて、伊東先生が「今からJ-GAP」とおっしゃらないと見逃すところでした。
伊東:プログラムではこの…(プログラムを開けて確認する)タイムテーブルのところだけに書いてあったようですね。前回大会(2012年に名古屋で開かれたICJLE)ではJ-GAPが前面に出てしまったので抑えたんですが…ちょっと少なかったようですね。
伊集院:確かになかなか気づいてもらえなかったかもしれませんね。
伊東:J-GAPの活動を推進しているグローバルネットワーク(GN: Global Network)は、9つの国や地域の日本語教育の代表者で作られています。今度からインドネシアが加わることになったのですが、グローバルネットワークはICJLEの運営にも大きくかかわっています。次回からもシンポジウムは行うと思いますので、ぜひ多くの方々にご参加いただいて、議論をしていきたいですね。
司会:2016年のICJLEがバリ島開催ということで、そのインドネシアのお披露目ですね。
伊東・伊集院:いいですよね、バリ!
伊集院:今回やっぱり7月ということで参加するかどうか本当に悩んでいて、ギリギリまでどうしようかと思っていたのですが、来てみて本当によかったです。2016年のバリはもう少し参加しやすい時期だと、JLCはもちろん、大学全体からももっと大勢来られるかもしれませんね。
伊東:一応日本側からは、次回はできれば8月に、ということで要望は伝えました。もちろんインドネシアの先生方の都合もありますし、どうなるか分かりませんが、みなさんがうまく集まれるタイミングだといいですね。
司会:それにしても、今回は終わってみれば大成功でしたね。
伊集院:当日は本当によくオーガナイズされていて、ボランティアの学生さんたちもすごく丁寧に接してくださって、とてもいいつながりができているということが分かりますよね。

伊東:Dr. Nunan(Dr. David Nunan)の基調講演もトムソン先生(トムソン木下千尋先生)のご発表もとてもよかったですし、佐藤先生のもすごくおもしろかったですね。私も地域関係の研究や実践をしているからかもしれませんが、やっぱりそういう「つながり」の大事さは身に染みているので、大変興味深かったです。
司会:日本国内の第二言語環境にいると、意識的に作らなくても学習者は社会とつながるだろうと思っているところがあるかもしれませんね。でも本当はそうではない学習者もたくさんいるわけですし、大学生対象でも地域でも日本国内の「つながり」も意識して作らないといけないですね。

伊集院:確かにそうですね。今回の学会は「つながり」というキーワードがとても際立っていましたよね。私の発表は最終日だったのですが、あれだけ大勢の方がCan-do(「Can-do statement」)に興味を持って発表を聞きに来てくださったのが大変ありがたかったです。大会のテーマが「つながり」で、最近のトレンドがCBIや活動型、社会につながるというところに向かっているので、実は、アカデミック・ジャパニーズの発表をするっていうのに少し不安もあったんですけどね。
伊東:そうだったんですか?
伊集院:はい。そんな中で発表してみましたけど、こういういろいろな人が集まっているときに発表すると客観視できるからいいですよね。その日本語教育学界の潮流に乗っているかどうか心配になるところはありますけど。
伊東:アカデミック・ジャパニーズの中に「つながり」というテーマがないわけではないし、全部いっしょ(の方向)ではないからおもしろいんですけどね。Can-doを作るのも一つの流れですが、本センターは「JLC日本語スタンダーズ」を作る時に何度も話し合いを重ねました。その時にかなり議論したところが今やっぱり活きてきていますよね。だからこそ、これからも自分たちがいま考えていること、JLCで取り組んでいることを発表して、ほかの先生方とも共有していくことが重要ですね。
伊集院:その点では、教員どうしや近くの大学との「つながり」をいっそう大事にしていきたいですね。拠点(文部科学大臣認定の「日本語教育・教材開発・実践教育研修」の教育関係共同利用拠点)としてもがんばらないと。
司会:そうですね。2年後に向けても…
伊東・伊集院:バリにむけても(笑)
司会:今後もセンターに乞うご期待ということで、拙い司会でしたが、今日はどうもありがとうございました。
伊東・伊集院:ありがとうございました。

参考URL
ICJLE2014 https://icjle2014.arts.unsw.edu.au/jp/
J-GAP http://j-gap.wikispaces.com/
謝 辞
本報告内の大会写真は、ICJLE2014大会事務局の記録写真を使用させていただきました。ご許可くださいました大会事務局並びに島崎薫先生、大会委員長のトムソン木下千尋先生に心から感謝いたします。