

内容:
コンピューター―人間は、この身近でありながら複雑難解な機械とどのように向きあってきたのか。今日、めまぐるしい進化をとげるコンピューターの世界にあって、比喩表現を用いて《未知なる存在》を理解しようとしてきた日本語の格闘の軌跡をたどる、応用認知言語学の新しい試み。
執筆者:
荒川洋平
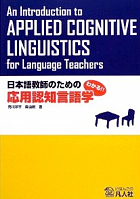
内容:
認知言語学は外国語教育にどのように応用できるのか? カテゴリー化、プロトタイプ、スキーマ、概念メタファー、UBMなど多彩な概念を平明に論じ、この分野の先駆けたる記述を目指す。
執筆者:
荒川洋平・森山新

内容:
日本語教師向けに、テスト問題の作り方の手順についてまとめたもの。「テストを作る前に」「文法テストを作る」「語彙テストを作る」「文字テストを作る」「作文テストを作る」「会話テストを作る」「読解テストを作る」「聴解テストを作る」「プレースメントテストを作る」の9章構成。
執筆者:
伊東祐郎

内容:
現在の言語テスティングについて最新の動向を踏まえ、今後の展開について説得力のある議論を提示。言語テスティングにかかわる広範囲な問題を簡潔にまとめ平易に解説した入門書。
執筆者:
ティム・マクナマラ(著)伊東祐郎・三枝玲子・島田めぐみ・野口裕之(訳)

内容:
日本語教師として必要な基礎知識を幅広く提供するために編まれた一冊。 読者が知識と技能を多角的に学び、実践につなげられるようになることを目的としている。 大きく2 部に分かれており、第1部では日本語および日本語教育についての基礎知識を概観し、 第2部では日本語教育の実践について考える。
執筆者:
阿部祐子・伊東祐郎・左治木敦子・佐野ひろみ・嶋津拓・杉山朗子・陳風・その他
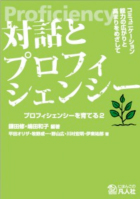
内容:
対話と会話の違いを知り、対話の本質を知ることは言語教育にどう関係するのか。対話を日本語教育に取り入れるとはどういうことなのか。このテーマについて、プロフィシェンシーと対話の関係を解説する0章とそれに続く4つの部「対話への指針」「実際生活における対話」「習得と教育」「総括」。さらに牧野成一と平田オリザの「対談」を通して紐解く。
執筆者:
鎌田 修、平田 オリザ, 牧野 成一, 川村 宏明, 野山 広, 嶋田 和子, 伊東 祐郎
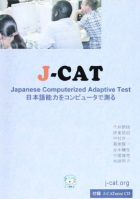
内容:
J-CAT(Japanese Computerized Adaptive Test)はインターネット上で日本語学習者が日本語能力を測ることのできるテストである。コンピュータとインターネットがあれば、誰でも、どこからでも、いつでも利用出来る。本書の目的は、J-CATを広く紹介し、使ってもらうことである。 本書には付録として、コンピュータ適応型テスト(J-CAT)を体験してもらうためのJ-CAT miniのCDが付く。
執筆者:
今井新悟・伊東祐郎・中村洋一・菊池賢一・中村彌生・中園博美・本田明子

内容:
水谷修先生(元・名古屋外国語大学学長)の、これまでの研究を5つのテーマに分類し、それぞれの分野から執筆者が集結した。
各巻は1テーマを概観するタスク、2先行研究の総括、3今ある問題や課題についての研究論文、4未来への展望と提言、という4部構成になっている。
日本語教育に関わる研究者や、大学生はもちろん、現場で活躍する先生方や教師を目指している方々など、日本語教育に携わるすべての方に贈るシリーズである。
執筆者:
野山広・石井恵理子・伊東祐郎・岩見宮子・嘉数勝美・小林悦夫・橋本博子ほか
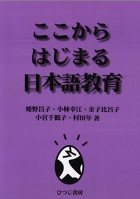
内容:
外国人に日本語を教える際の基本となる、書くこと、話すこと、読むこと、書くことなどの指導のポイントや、様々な教授法について具体的な事例を多く用いて分かりやすく解説する。

内容:
主な形式名詞を基礎とする複合述語や文中表現を体系的に解説したもの。
執筆者:
吉川武時(元センター教授)執筆者代表:小林幸江・柏崎雅世(元センター教授)
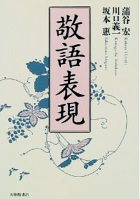
内容:
狭い意味での敬語を正しく使っているだけでは、円滑なコミュニケーションは期待できない。「敬語」が用いられている「表現」全体をとらえて、「敬語表現」を説き明かす。
執筆者:
蒲谷宏・坂本惠・川口義一

内容:
「だれが、だれに、だれのことを」、そして「どういう時に、どういう所で、どういう状況で」、敬語を使うのか? 従来の「尊敬・謙譲・丁寧」などの分析的な捉え方を抜け出して、コミュニケーションの中で敬語を考え直す。
執筆者:
蒲谷宏・坂本惠・内海美也子・川口義一・清ルミ
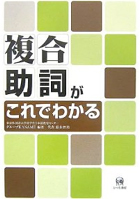
内容:
「について」「に関して」など、初中級レベルで導入される複合助詞の形式的特徴および意味・用法を詳細に、かつ日本語教育の現場で役に立つよう、ポイントを明確に押さえて解説。
執筆者:
東京外国語大学留学生日本語教育センター・グループKANAME(代表・鈴木智美)
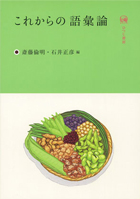
内容:
語彙論の基礎とともに、フェミニズム、民俗学、認知言語学、対照言語学、日本語教育、コーパス言語学、情報学などの立場から語彙研究を紹介し、今後の語彙研究の可能性を展望する。
執筆者:
斎藤倫明・石井正彦(編)/小野正弘、影浦峡、笹原宏之、佐竹久仁子、佐竹秀雄、定延利之、鈴木智美、高崎みどり、田野村忠温、町博光、屋名池誠、由本陽子

内容:
元センター教授・柏崎雅世氏(現・朝日カルチャーセンター日本語科)の退職記念論文集。論文28本を収録。

内容:
人と人が会話をして友好な関係を作っていくには、語彙・文法等の言語能力だけでなく、会話に参加していく社会言語能力や、実質的な行動していく社会文化行動といった「インターアクション能力」が必要である。本書は、こうした能力育成を目的とした日本語の会話教育を開発するための「研究と実践の連携」のあり方を提案するとともに、教育法案を具体的に提示した。特に、教師と学習者が会話データ分析をした成果を指導学習項目化し、それを教育実践に生かすプロセスを詳述した。
執筆者:
中井陽子
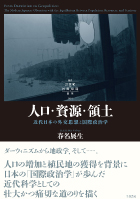
内容:
一方で日本には、19世紀後半から全世界を席巻していた進化論が入ってきていた。他方で、日本は領土に比して人口が大きすぎると考える風潮が高まりつつあった。
本書では、この二つの思想が合わさって殺伐とした国際関係のイメージが立ち現れる様子と、それを理論的に克服するために国際政治学と呼ばれる学問が立ち上がるにいたる過程が、加藤弘之、有賀長雄、建部、小野塚喜平次、神川彦松の五人に焦点をあてて描き出されている。
執筆者:
春名展生
編者:
小田川大輔、五野井郁夫、高橋良輔
執筆者:
上原賢司、清水耕介、多湖淳、芝崎厚士、春名展生、西平等
*「第7章 近代日本における国際政治論の展開」
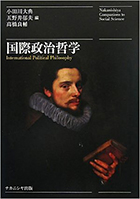
編者:
石堂典秀
執筆者:
金敬黙、土井崇弘、飯尾歩、安村仁志、張勤、中西真知子、羅一慶、山中仁美、渋谷努、春名展生、上代庸平、古川浩司、京俊介、大友昌子、檜山幸夫

内容:
多くの意味を持つ日本語の基本的な名詞121を認知多義理論から分析・再構成してネットワーク図とイラストで示した学習辞典。「多義語学習辞典シリーズ」の第1弾で、『形容詞・副詞編』『動詞編』が続く。
執筆者:
荒川洋平

内容:
日本語教育に携わる人を対象にし、日本語教育に関わる重要分野を広く網羅した用語事典。代表的な基本用語と重要用語を厳選して、最先端の知見を結集し詳細にわかりやすく解説した。情報の検索はもちろんのこと、基本学習用に使える推薦文献も掲載して、各分野の学習用にも使えるオールマイティな教育用語集としても活用できる。日本語教師を志す人や、日本語教育能力検定試験の受験者にも威力を発揮。
編執筆者:
近藤安月子・小森和子
執筆者:
伊集院郁子
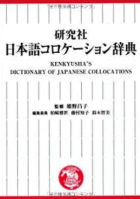
内容:
コロケーション(語と語の慣用的な結びつき)に着目した画期的な日本語辞典。動詞、形容詞、形容動詞を見出し項目とし、4万5000を超える生きた例文を収録。(『研究社 日本語表現活用辞典』(2004)を大幅に増補した改訂版)

内容:
「さすが」「もったいない」「そろそろ」「なるほど」など、初・中級レベルの説明の難しい語彙を題材に、現役日本語教師から説明を公募。秀作を講評。具体的に教室でどう説明すればよいかヒントが見つかる。
執筆者:
鈴木智美・春原憲一郎・星野恵子・松本隆・籾山洋介
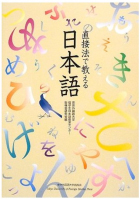
内容:
日本語力を高めるための授業、全28課。長年の蓄積をふまえた最も適切な場面設定、説明用の台詞、留意点など効果的な指導法をていねいに解説。わかりやすくスムーズに教えられる日本語教師待望の手引き。導入に便利なカラーイラスト433枚付き(CDに収録)。

内容:
本シリーズは教科書・教材作りのプロセスとノウハウをテーマ別にまとめたシリーズである。本書では会話教材を取り上げ、会話教育の理論を説明するとともに、現場の教師が実際の授業で使用した教材を用いて、その授業や授業の結果を報告している。実際の教材や実践報告を通して、各教育現場での会話教材作成のヒントや、会話教育について考える際のヒントが得られる。
執筆者:
尾崎明人・中井陽子・椿由紀子
編者:
関正昭・土岐哲・平高史也
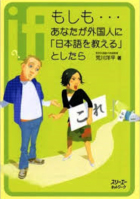
内容:
ちょっとした工夫で「日本語を教える」ことを外国人へのプレゼントにできることを説いた実用的な読み物。第1章、第2章は授業準備と授業の実況中継で、初めて日本語を教えることになった3人の登場人物の授業の試行錯誤を通し、日本語教育の初歩と指導のポイントを具体的に解説。第3章では授業準備、導入などから復習まで授業の流れにそって「教え方の枠組み」を解説。第4章「扉の向こうへ」では日本語教育の世界を概観。
執筆者:
荒川洋平

内容:
前作に引き続いて登場する「いきなり先生」3人に加え、今回は海外で日本語を教えることになった新たな「いきなり先生」が登場。著者の経験をベースにしたそれぞれの「いきなり先生」の授業の実況中継を通して、外国人に「日本語を教える」際に直面するさまざまな問題を明らかにしていく。特に今回は、教科書や教材・教具について具体的な例を挙げてわかりやすく解説。
執筆者:
荒川洋平
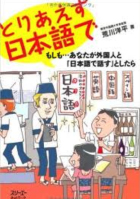
内容:
これからの日本は、外国人が今よりもさらに増えていくことが予想され、日本語学習者も確実に増えていく。つまり私たちは外国人と日本語で話す機会が増えていくことになる。しかし、実際外国人と日本語で話すとき、どのような話し方、接し方をしたらいいのか、不安に思う人も少なくないだろう。この本では外国人と日本語でやりとりすることを、さらに外国人どうしが日本語でやりとりすることを「対外日本語コミュニケーション」と名づけ、様々な場面で実際に起こりうる例をもとに考察し、問題点や解決法を探っていく。
執筆者:
荒川洋平
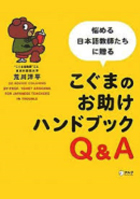
内容:
「教科書は順番通りに教えなきゃいけない?」。誰もが一度は抱くこんな悩みに、QA形式でわかりやすく答える。日々の「なぜ?どうしたらいい?」を大切にし、常に考える教師を応援する1冊。
執筆者:
荒川洋平

内容:
日本人が考える「日本語」と外から見た「ニホンゴ」は違う。「どこが難しい?」「意外な魅力とは?」「どう教えるか?」豊富な日本語教育経験から語る、日本人のための日本語再入門。
執筆者:
荒川洋平
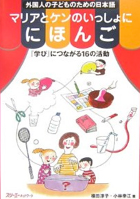
内容:
外国人に日本語を教える際の基本となる、書くこと、話すこと、読むこと、書くことなどの指導のポイントや、様々な教授法について具体的な事例を多く用いて分かりやすく解説する。
執筆者:
横田淳子(元センター教授)・小林幸江

内容:
大学で学ぶために必要な「講義や口頭発表を聞く力」を養成するテキスト。 単なる聞き取りにとどまらず、全体の構成を把握するための練習や、要約を書く練習もある。各課の内容は「富士山、隠れキリシタン、ゴリラの食事、失敗学、津軽三味線、東京の温泉」など、日本文化・歴史に関するものから、自然科学のへの足がかりとなるものまで、留学生が興味を持って聞けるテーマを集めた。 本文総ルビ、全15課。別冊(スクリプトと解答)、音声CD1枚付。
執筆者:
東京外国語大学留学生日本語教育センター

内容:
●内容を大まかに捉える練習 ●要点をまとめて答える練習 ●要約文を書く練習を通して、話者の言いたいことを適切につかむための練習が段階を踏んでできる構成になっている。
テーマは日本の社会や文化に関する、〇新幹線のおでこ、〇体験プレゼント、〇女性専用車両、〇剣道、〇落語など、留学生が興味を持って聞けるものを集めた。音声は付属のCDのほか、動画をダウンロードして聞くこともできる。
執筆者:
東京外国語大学留学生日本語教育センター

内容:
準備中
執筆者:
東京外国語大学留学生日本語教育センター
内容:
文部科学省検定済み 高等学校外国語科用教科書の教師用指導書
執筆者:
八宮孝夫、手島良、中村彰、渡辺信幸
内容:
文部科学省検定済み 高等学校外国語科用教科書の教師用指導書
執筆者:
八宮孝夫、手島良、中村彰、渡辺信幸