
今回ご紹介する先生は、世界社会言語センター所属の岡葉子先生です。JLCでは全学日本語プログラムのコーディネート、ご出講に加え、IJ共学のお仕事にも携わってらっしゃいます。
私はことば以上に「人」に興味があります
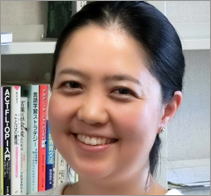
インタビュアー(以下、I) 本日はお忙しいところ、インタビューをありがとうございます。ご出身は東京でいらっしゃいますか。
岡先生(以後O)はい、世田谷区の世田谷で、上町というところです。世田谷と言っても、とても下町の感じが残るあたりです。
I)小さいころは、どんなお子さんだったんですか。
O)自分で言うのも何ですが(笑)面倒見の良い子どもだったと思います。三つ下の妹がいるんですが、よく面倒を見ていました。
I)そうですか。で、中学から高校は国立の難関校(お茶の水女子大学付属中・高)で勉強されたんですよね。他の先生たちと同じように、このころから言語への関心が芽生えていらしたのですか。
O)いえ、それが全然(笑)。一学年が100人程度の小さい学校だったんですが、とにかくバラエティに富んだ友達がたくさんいて、面白かったです。部活でテニス部とワンゲル(ワンダーフォーゲル)部の両方に所属していました。学校が大好きなので、卒業してからも当時の顧問の先生たちと用務員室で焼酎を飲んだり(笑)。
I)何だか男子校の思い出を聞いているみたいですね(笑)。当時の愛読書とか、影響を受けた文学作品などはありますか。
O)有島武郎が好きで、よく読んでいました。「生まれ出ずる悩み」とか「或る女」とかですね。特に「或る女」はヒロイン(早月葉子)が同じ名前なので、親しみを持って読みました。
I)で、その後進まれた慶應義塾大学では西洋史を専攻なさったとのことですが、これはどうしてですか。
O)これも高校の影響で、世界史の授業と先生がすごく好きだったんです。また当時、ソ連の民主化とか、東西ヨーロッパに大きな変化があったりしたので、もっと勉強したい、と思って東欧史を学びました。
I)欧州へは留学もされたんですか。
O)はい、大学4年のときにドイツのザールランド大学へ交換留学で1年、行きました。フランクフルトからさほど遠くない町なんですが、ドーデの『最後の授業』で有名なアルザス・ロレーヌ地方にも近いんです。ドイツは土日、スーパーとかが完全に休みになるので、特別な許可証をいただいて国境越え(笑)をしてパンを買いに行ったりしていました。
I)そうですか。なかなか日本語教育になりませんが、その後、大学院ですよね。
O)ちょっと待っててください、そろそろですので(笑)。留学後、興味が地域研究、と国チェコやオーストリアの地域研究になったこともあり、大学院は本学、つまり東京外大にしましたで、卒業後に勤めたNPOの仕事で、2006年までモンゴルに行ったんです。ウランバートルの日本研究センターで仕事をさせていただけることになって。
I)そこで日本語教育を始めたのですか。
O)はい、初めは事務職で入ったのですが、そこの図書館にはたくさんの蔵書があったので勉強して、2003年の8月が教師デビューでした。いろいろな方に支えられて、このキャリアを踏み出すことができました。
I)その後、帰国されてから今までずっと、日本語教師をなさっているわけですね。
O)はい、2006年に帰国してから文化外国語専門学校で、2007年からは東中野にあるイーストウェストインスティチュートでお世話になりました。その間、また東京外大の大学院に入りなおしました。今後は日本語教育の専攻です。2つ目のマスター(修士号)ですが、そのまま博士後期に所属して現在に至ります。
I)今、専任教員(助教)のお立場としてコース運営などに関わっていますが、この仕事の面白さはどこにありますか。
O)そうですね。私、非常勤の立場も長いんですが専任になってから見えてくるものも多く、やりがいを感じます。非常勤の先生方のお得意な分野をどうプログラムに反映させようとか考えたりすると、重圧ではあるけれど面白いと思います。
I)なるほど。そう伺うと、岡先生はことばへの興味はもちろんおありでしょうけれど、それ以上に「人間」が好きなのかな、と思います。
O)はい、それはあると思います。歴史学も言語教育も人に関わることですし、現在の研究テーマも動機付けなのですが、これからも日本語を「人に」教えることを意識していきたいと思っています。
I)今日はありがとうございました。
O)こちらこそ、ありがとうございました。