
JLCで授業をご担当なさっている先生方をご紹介しております。
今回ご紹介するのは、2015年4月に本学に着任なさった春名展生先生です。
春名先生は、今夏『人口・資源・領土 近代日本の外交思想と国際政治学』(千倉書房)を上梓なさいました。このインタビューはその少し前、夏休みが始まってすぐのころにお願いしたものです。春名先生の誠実なお人柄にふれることができました。
教師として、民主的な社会の建設に寄与していく
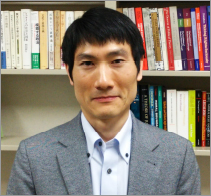
インタビュアー(以下、I) 今日はお忙しいところ、ありがとうございます。夏休みとなりましたが、改めて、第1学期を終えられてのご感想をお願いします。
春名先生(以下、H)
体力的には厳しかったと思います。一年目ですから過去の蓄積がなく、直前まで準備して授業に臨むという自転車操業の日々でした。そんな中、知的好奇心と向学心にみちた学生たちの存在は励みになりましたね。そのおかげで、次の学期も前向きに迎えられます。
来年以降は、授業の準備にかかる時間が多少は減るでしょう。それで少しは研究に回せる時間が増えると思いますが、教育と研究のバランスを考えた場合、もう少し研究に専念できる時間があるとありがたいですね。今年の場合、7月31日に日本語・日本文化研修留学生プログラム(日研生プログラム)の教育を終え、それから学期中には手が回らなかった仕事に取り組んでいますが、すぐまた第2学期の授業が始まりますし。
I) そうですか。日本語のレベルが様々な学生さんのために授業を準備する、というご経験は、これまでそんなに経験する機会のないことではないかと思いますので、そういった点でもご苦労なさったのではないかと思います。春名先生の場合、複数のプログラム・コースで授業をご担当なさっていますが、それぞれの学生の違いも新鮮だったのではないですか?
H)
そうですね。1年コース(国費学部進学留学生予備教育プログラム)の学生たちも、日研生プログラムの学生たちも、向学心が旺盛な点で差はありませんが、1年コースの学生たちは希望する大学に進学するために競争にさらされているという点で、日研生たちとは置かれている立場が大きく違います。
そのため、教員としましては、学生の性格や能力が違うからではなく、置かれている立場が違うため、二つのコースで教育の内容や方法を変える必要があると考えています。1年コースの学生たちに対しては、厳密に数値で成績がつけられるような考査をおこないますから、それに適合した教育をおこなう必要があるのです。
I) なるほど。授業ご担当も含め、ご着任前に抱いていたイメージやご着任後に考えたことなどはギャップのようなものがありましたか。
H)
着任前にいただいた資料から、1年コースの学生たちの希望進路が変わってきていることを知りました。かつては経済や経営が多数を占めていましたが、この十年ほどの間に人文学系を志望する学生が増え、多様化が進んだようです。今年も、この傾向にそった専攻の分布が見られるのではないでしょうか。
着任して以来、いろいろな先生方とお話して、国を背負うような気概にみちた留学生が減ったとか、きらりと光る才能をもった留学生が減ったと耳にしましたが、これも同じ変化に原因があるのではないかと思います。要するに、「日本には本国にない先進的な知がある」と信じて来日する学生が減ったのではないでしょうか。
私は、何も日本の教育が劣化したと言いたいのではありません。本国にも充実した教育制度があって、本国にいても高度な教育を受けられるような国から来る留学生たちが増えたのではないかと思うのです。国費留学生の選抜にあたって日本語の試験を課せば、そのような結果は必至でしょう。
本国にも高水準の教育研究機関があるのであれば、日本からすぐれた技術や知識を持ち帰るという発想はわきません。そのような国から来た留学生は、本国でも学べるような学問ではなく、日本でしか学べない学問を専攻に選ぶでしょう。日本語学専攻が増えている背景には、このような事情があるのではないでしょうか。
また、図抜けた才能を見せる留学生が減ったのは、教育制度が整った国で標準化された教育が行き届いていることが一因ではないかと思います。
このような見立てが正しいならば、以前よりも「目が肥えた」留学生たちが増えると考えられます。つまり、悪くいえば「うるさい」留学生が増えるのではないでしょうか。その点で教員にとっては難しい時代が来るのかもしれませんね。笑
I) そうですね。笑 アンケートを見ていたりすると、はっきりと意見を書く学生が以前より増えたような気もしますね。
H) しかし、それでも、この変化は好ましい方向を向いているのではないかと思います。国家間の関係が、より平等になっていることのあらわれのように感じられます。
I) そうですね。本学でも世界の大学との「頭脳循環」として、研究者間のネットワーク構築を目指していますが、日本で学びたいと考えている学生さんが何を身につけ、また本国、日本、世界のために社会に羽ばたく第一歩やその過程に、我々がかかわっていることの意義を改めて考えていきたいところですね。第2学期以降、先生の授業内容も、第1学期のご経験から新たな展開を迎えそうな気もしますが、いかがでしょうか。
H)
第1学期の経験は、あまり活かせないですね(笑)授業の内容が変わりますし、学生たちの緊張感も増しますから。
第2学期は「政治経済」が週3コマ開講されます。その3コマを「日本の政治」、「日本の経済」、「日本の外交」に分け、内容としましては、できるだけ体系的に政治学、経済学、国際政治学の基礎を学ばせたいと考えています。
もう一つ、「日本事情」という科目を担当しますが、その具体的な内容につきましては、まだ思案しているところです。「政治経済」では取り上げないものの、日本の政治や社会を考えるうえで避けては通れない天皇制などにはふれたいと考えています。
I) 楽しみですね。私も日本語科目担当として、専門科目と日本語科目が一緒になって学生さんのこれからを支えていけるように頑張ろうと改めて思いました。今日はお話を聞かせてくださり、ありがとうございました。ちなみに、夏休みの間にリフレッシュする機会はありそうですか?
H)
夏休みは、1週間ほどですが、スイスに出かける予定です。新任のくせに何て金回りが良いのかと思われそうですが(笑)、スイスを旅先に選んだのには、特別な事情があります。
いまジュネーヴに、大学院で同期だった友人がいるのです。彼はフィンランド出身ですが、日本で日本政治について研究したあと、本国に帰って外交官になりました。そしていま、その友人がWTO(世界貿易機関)のフィンランド政府代表部にいるのです。
現在、留日センターの留学生たちがはぐくんでいる友情も、後々大きな財産になるかもしれませんね。
I) 出会いは大きな財産ですね。最後に、もうすぐご出版なさるご著書について、お伺いできますか。
H)
やや専門的な話になりますが、この本は、進化論の受容と敷衍に焦点を当てながら、日本における国際政治学の成り立ちを描いたものです。
ご存知のとおり、ダーウィンは、生物の個体数が環境の収容能力をこえて増殖するために生存競争が発生するという生物学の理論を打ち立てました。これに着想を得て、人口の増加や「過剰人口」の発生が、資源や土地をめぐる国家間の闘争を不可避にするという国際関係の見方が形成されたのです。
ただ、ここで注意を要するのは、「過剰人口」とは、単に人口が増えるから発生するものではなかったということです。職にあぶれ、食にありつけない人々が「過剰人口」と呼ばれていたのです。ですから、簡単にいうと、失業と貧困が「過剰人口」を生むということになります。明治時代の後半以降、このような「過剰人口」の存在が社会問題になり、それとともにアカデミズムの中で殺伐とした国際関係の見方が確立されていくのです。
この見方は両刃の剣でした。それは一方で、植民地の獲得を正当化する論理になり、闘争を基調とした国際関係の存続に寄与します。しかし他方で、それは国際関係の根本的な改革を求める根拠にもなります。とりわけ、資源の国際的な管理と分配、あるいは国際的な人の移動の自由を主張する根拠になります。このような思索が、国際連盟の創設という現実的な基盤を得て、「国際政治学」と呼ばれる新たな学問分野の確立につながったのです。
ずいぶんと本の宣伝に時間を割いてしまい、失礼いたしました。
I) 実際の社会のできごとのとらえ直しが学問によってなされるというお話は、1年コース、日研生両方の学生にとって今後の進学、研究において重要な考え方につながりますね。留学生の皆さんにとっても大きな財産になる出会いになると思います。そういった学生を育てていくことはJLCにとっても大きな財産ですね。本日は本当にありがとうございました。