
2014年4月、JLCは新しく2名の専任教員を迎えました。
今月と来月の2回に渡って、お二人のインタビューを掲載いたします。最初は、石澤徹先生です。
誰のための、何のための研究か
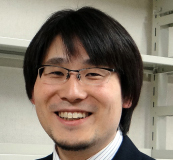
インタビュアー(=Q):赴任直後であわただしい中、今日はありがとうございます。初めにお生まれと、子ども時代のご自身についてお話していただけますか。
石澤専任講師(=A):生まれたのは、奈良県の橿原市です。大学で広島に行くまでは、ずっとそこにいました。子供の頃はいろいろ好きなことがあったのですが、地元の子どものサッカーチームに入っていて、卒業後もOBとして(笑)手伝いに行っていました。学校は大阪の天王寺区にある、上宮中学・高校に進みました。
Q:中学・高校時代はどんな科目が好きだったんですか。
A:誰でもそうだと思いますが、やはり担当された先生によって好き嫌いがけっこう決まるというか、初めは国語が好きだったんですが、だんだん英語の方が好きになってきて、中学校のおわりからは逆転しました。僕、B'zと、それから洋楽もずっと好きで、歌の発音とかにも単純にあこがれていた、みたいなところもありました。で、なんとなく教師志望だったのですが、国語の教員になるか、それとも英語の教員になるか決めかねていたところ、両方取れると思うと高校の先生に勧められ、広島大学教育学部の日本語教育系コースに進むことにしました。
Q:今回、東京の大学に赴任なさったわけですが、広島大学はこういう首都圏の大学と比べて何か違いがありましたか。
A:そうですね、広大ではみんなキャンパスの周りに住んでいたので、飲み会とかもみんな近いところになっていましたが、東京だと誰かが銀座で飲み会をしよう、というと別の誰かが、いや新宿のあそこの店がいい、みたいに駅が、あの、飛びますよね(笑)。これは新鮮な体験でした!
Q:そうですか(笑)。では話を戻しまして、その、日本語教育に目覚めたというのは、大学時代になるわけですか。
A:そうです。入学してすぐ、日本語教育系コースの新入生歓迎のお花見があって、隣に座った先輩から、広島市内で外国人に日本語を教える会があるんだけど、と言われて、市内に出るきっかけにもなるし、ということですぐ決めました。
Q:躊躇しなかったんですか。
A:中高を過ごした上宮というのは仏教系の学校なんですが、「縁」というのを大事にしなさい、という教育をするんです。ですので、ここで出会ったのもご縁かな、ということで決めました。
Q:あぁ、なるほど。で、実際にどんな活動をどのくらいしたんですか。
A:初めは土曜日だけだったんですが、楽しくて、もっと機会を持ちたいと思って、広島市内と東広島市内とのボランティアを掛け持ちし始めて、多いときは、週3回するようになりました。で、東広島市内のほう一本に絞って、何かユニークなことをしようということで、夏休みは機能場面シラバスでプログラムを進めたりしました。
Q:一学部生の立場で、すごいですね。広大の留学生センターの先生かどなたかに指導を仰いだのですか。
A:いえ、それが指導者なしで(笑)。今考えると、無謀でした(笑)が、中心メンバーだった同級生たちと、よく明け方まであーだこーだと話し合っていたことを思い出します。そういえば、初めて敬語の授業をすることになったときは、当時1年生でまだ面識もほとんどなかったんですが、横溝紳一郎先生(現・西南女学院大学)のところへ押しかけたりしました。今でもお会いすると、その頃のことをお話されることがあります。
Q:おぉ、武勇伝ですね。で、さきほどお話されたどちらの教員になるか、という件はどうなったのですか。
A:当時、広島大学の教育学部は教員免許の取得が卒業要件だったのですが、日本語教育専攻は、いわゆるゼロ免という、これが要件になっていない学科なんです。ただ、教育実習に行くことにすると、英語ではなくて国語になってしまうということで…そこで、じゃあ国語も英語も取ればいいや、と。大学院には最初からなんとなく行く気でしたので、6年かければ英語も取れるだろうということで、そのまま進みました。
Q:でも高校の先生にはならなかったんですね。そのあたりは何か、いきさつがあったのですか。
A:はい、大学院に進むと決めたころから、外国語としての日本語教育、そして教育そのものよりも教師養成に興味が出てきたり、広大の留学生やその家族だけでなく、生活者の方や中国帰国者の方の支援を少しお手伝いしたり、あと子どもの言語習得も面白いと思ったり、アメリカ滞在中に継承語について知ったりと、さまざまな日本語教育や言語教育に携わっていく中で、研究も教育もする大学の教員をめざすようになりました。
Q:大学での日本語教師デビューはいつだったんですか。
A:修士の途中で、ご縁があって、アメリカのサウスカロライナにあるファーマン大学のランゲージ・ハウスというところでTAとして教えたのが最初です。それから院生のときは日本語学校や広島県のひろしま国際プラザや大学などで教えたりして、博士修了後は山口福祉文化大学(現・至誠館大学)の東京サテライト教室で数年仕事をして、今回、東京外大でお世話になることになりました。
Q:なるほど。では最後に今後の抱負を聞かせてください。
A:はい、まず何より本学の仕事に慣れるのが大事だと思います。まだいろいろ複雑で覚えなければならないことがたくさんありますが、授業が始まれば、教育で集中すべきことは定まってきますので、留学生のモチベーションを大事にして教えていきたいと思っています。研究については、自分の専門である音声教育分野だけでなく、基礎研究も含めて興味ある分野にしっかり取り組み、柱を作りながら裾野を広げていきたいと思います。授業では特定の学生を相手にしますが、研究はそれだけではないので、より広く、誰のための、何のための研究かを考えつつ、しっかりやっていきたいです。
Q:そうですか。今日はどうもありがとうございました。