
このページでは1ヶ月に1回、当センターの教員へのインタビューや、センターが研究・開発中のプロジェクトに関する情報提供を通じて、国内最大の留学生教育機関であるJLCTUFSの「いま」を伝えていきます。
12回は全学日本語プログラム、ISEPご担当の伊集院郁子専任講師へのインタビューです。
何事にも真摯に取り組む姿勢を忘れなければ、回り道はいつか回り道でなくなる
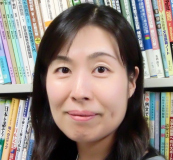
インタビュアー(=Q):今日はお忙しいところ、ありがとうございます。先生、お生まれは東京ですか。
伊集院専任講師(=A):はい、生まれは東京の渋谷です。公園通りの繁華街で育ちました。4歳くらいまでは父の仕事の関係でアメリカのイリノイとベルギーのブリュッセルにもいたんですが、ほとんど記憶がなくて…。母の話では、姉とフランス語で口げんかをしていたというんですが…(笑)。
Q:そのまま渋谷に?
A:いいえ、小6のときに三鷹の方に越して、あとは市立の中学、都立高校、大学とずっとそこにいました。
Q:子どもの頃の愛読書とかは、何かありますか。
A:そうですね、女性の人生を描いたものとかは好きでした。ミッチェルの『風と共に去りぬ』とか、あと三浦綾子の『氷点』などですね。
Q:大学は上智で英語専攻でいらしたそうですが、子どもの頃の外国経験とかは影響しているんでしょうか。
A:いえ、それが全然。高校までは英語より数学の方が好きだったくらいで。ただ、まあこれからは語学は出来た方が良いかな、という気持ちがあって、それで選んだんですが。
Q:日本語教育との出会いは、大学からですか?
A:いいえ。勉強はずっと好きだったんですが、卒業後はとりあえず一般企業に就職して、秘書室に勤務していました。その時に言葉の使い方の難しさを痛感したり、オーストラリア人の同僚に日本語について聞かれたのがきっかけで、気付いたらアルクの通信講座(NAFL)で勉強を始めていました。ですから日本語教育との出会いは、卒業後になりますね。
Q:じゃあ個人レッスンが長かったのですか?
A:個人レッスンを始めたら、もっと専門的な勉強がしたくなりまして、当時、あの、永福町にあるアルクの上で日本語教師の勉強会があって、それに参加したりするうちに、だんだん世界が広がってきた感じです。ジョーダンの Japanese: the Spoken LanguageやJBP (Japanese for Busy People)を使って外資系企業の方とかに教えているうちに、だんだんこれを一生の仕事にしたいと思うようになりました。で、思い切って会社を辞めてから、日本語学校などでも教えるようになりました。企業勤務は4年と少しの間だけでしたが、何にも代え難い、いい経験だったと思っています。
Q:そうですか。それから大学院に進まれたわけですね。
A:はい。国際学友会などでも採用していただいて、複数の機関で教えていた上に大学院ですから、何より近いところがいいと思って(笑)、東大の駒場に進みました。そこで尊敬できる研究仲間も得られましたし、指導教員の近藤安月子先生からは、研究にも教育にも誠実に取り組む姿勢を学びました。で、修論を書き終えたときに、学友会を通じて、このセンターの長春派遣の非常勤講師に採用されたのが、本学とのご縁の始まりです。
Q:ご研究が徳川宗賢賞(注:社会言語科学会の萌芽賞)を受賞されたのは、その後ですか。
A:そうです。その後、神奈川大学と本学の非常勤を経て、2006年に専任として着任しました。
Q:ご着任以来、携わったお仕事はどのようなものですか?
A:最初の5年間はずっと1年コースに携わりました。今年から全学日本語プログラムに移り、この9月からはISEPも担当しています。
Q:そのほかのお仕事もお忙しそうですね。
A:将来計画検討委員会の委員長もありますし、国際日本研究センターの兼任教員にもなりましたので、まさに今、また新たな勉強の時期、と感じています。
Q:現在、日本語関係での研究や関心はどのあたりにあるのですか?
A:私は話を伝えるときの方法、つまり「どう」というところに長く関心があって、賞をいただいた論文では初対面会話のスピーチスタイルの分析をしたのですが、現在は書き言葉、作文の研究をしています。論理的な意見文などを「どう」書くかに関心があります。
Q:そうですか。最後に、今後、日本語教育を志す読者に、メッセージをお願いいたします。
A:そうですね、私の場合は企業勤務の期間もあるし、ここに来るまでにすごく遠回りをしてきたようなんですが、今思うと、会社勤めでも学生時代の勉強でも、この仕事に役に立っていないものはないと思います。日本語教育は裾野の広い分野で、常に人間に関わり合う仕事ですから、与えられた環境でどんな事でも一生懸命やっていれば、それは必ずいつか何かにつながっていくと思います。
Q:本日はありがとうございました。
インタビューを終えて─
インタビュー前、伊集院先生は自分がこれといってしてきたことがない、と謙遜なさっていたが、伺っていくと、どの場面でもお話が深く面白く、今までのインタビューでは最長の時間になってしまった。その「深さ」はそれぞれの場での出会いを大切にし、努力と知性でその経験を確実にご自身のものになさっていらしたが故の達成ではないだろうか。大学人が組織の一員として動くことがいかなる時代にも増して求められる現代に、伊集院先生をファカルティの一員として持てるJLCは幸福だ、という印象が残るインタビューだった。