
このページでは1ヶ月に1回、当センターの教員へのインタビューや、センターが研究・開発中のプロジェクトに関する情報提供を通じて、国内最大の留学生教育機関であるJLCTUFSの「いま」を伝えていきます。
第8回は日本語ご担当の中村彰准教授へのインタビューです。
この仕事の面白さはダイナミックな緊張感
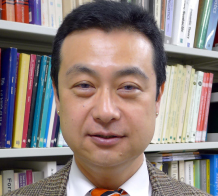
インタビュアー(=Q):今日はお忙しいところ、ありがとうございます。お生まれはどちらなんですか。
中村准教授(=A):生まれは、東京の板橋区です。
Q:帰国子女でいらしたんですか。
A:いえ、全然。外国に行ったのは、大学4年になる前の春休みに出かけた台湾が初めてです(笑)。
Q:でも先生は、本学では日本語ご担当ですが、東工大では英語の先生もなさっておいでですよね。何かこういう仕事に就くためのきっかけというのは…?
A:そうですね、もともと言葉が好きということもあり、中1で英語に初めて出会った時に、今までにない科目だ、面白いと感じました。それからずっと英語が好きだったので、この大学の英米語科に入学しました。学部生の時はずっと英語を生かした仕事に就きたいな、と思っていたんですが、結局、サラリーマンにはなりたくなくて、東大の大学院に進みました。東大では生成文法を研究したかったので、長谷川欣祐先生に教えを受けました。
Q:その時点では、まだ日本語教育とはご縁はなかったんですね。
A:ええ。東大大学院在学中に、奨学金を貰ってアメリカへ留学したのですが(編注 UCLA カリフォルニア大学ロサンゼルス校)、2年目に日本語のTAをやることになりまして、それが最初のきっかけです。
Q:初めて授業をなさって、どうお感じになりましたか。
A:アメリカの授業は教授の先生が大教室で文法のルールを説明し、それから小教室でTAと学生がディスカッションをするのですが、とても面白いと感じました。それまでは日本語は母語なので、考えなくても話せるのですが、ここで始めて、日本語を言語として客観的に見る経験を持ったことになります。英語だと、例文の文法性の判断にどうしてもネイティブのチェックを受けなければならない訳ですが、日本語だと教える場合に、母語話者の直観があるわけで、それを使えるのが良いと思いました。
Q:それから本学にいらしたわけですね。
A:そうです。生成文法の研究もしていたので、大学で英語を教える教員も希望していたのですが、外語は母校でもありますし、日本語教育も面白くなってきたので…。このセンターに赴任したのは、1995年の4月です。
Q:アメリカでなさっていたこととJLCの教育との違いに、とまどったりされませんでしたか。
A:もちろん! とにかくスピードが速いし、覚えさせる量も多いし…。何より僕は今はないですが、学習スタイルの違う学生を集めた「3コース」を中心に持っていましたので、1学期の試験なども独自に作ったりして、大変でした。ただその一方で、面白いこともたくさんありました。
Q:たとえば、どんなことでしょうか?
A:ある南米の国から来た学生だったんですが、まだ初級で知っている文型も単語も語句限られているのに、日本語で詩を書いたから添削してくれ、って言うんですよ(笑)。まあ添削しましたけど、それだけではなくて、たとえば3コースでは、ナイジェリアやセネガル出身といっ留学生たちに教えたんですが、逆に自分が多文化を教わったように思います。
Q:1年コースのあとはどんな教育プログラムに関わったのですか。
A:REXを3年やりました。予算が比較的潤沢だった期と、減額になった期と両方を経験しています。それから長春に行き、帰ってからは日研生プログラムに関わっています。
Q:そうですか。では研究に話を戻して、現在の学術的な関心について話していただけますか。
A:関心は変わらずに生成文法にあるのですが、日研生を担当するようになってからは対照言語学に生成文法の理論を組み合わせたような研究が面白いと思っています。日研生の国籍は多様ですから、たとえばテンスの問題とか、あるいは「自分」など再帰代名詞的な言い方は母語ではどの範囲を示すかなど、面白い発見があります。
Q:インフォーマントとしては最高ですね。
A:そうですね、みな日本語が堪能ですし。あと学生の多言語環境ということを考えると、鈴木智美先生が精力的に主導なさった作文コーパスにも、とても興味があります。やっとCD-Rom化されたので、これからいろいろ見て行きたいと思っています。
Q:ありがとうございました。最後に、これから日本語教師を目指す方にメッセージをお願いしたいのですが。
A:柔軟な発想を持つことですね。とかく、日本人は、とか、わが国は、とか一般化して考えてしまいがちですが、そういう先入観なしに日本語や日本文化について柔軟に考えていくことが、特に若い人には大切だと思います。そこから新しいものを上手に切り取ることができますし、オリジナルな研究や教育が始まると思います。
Q:今日は長い時間、ありがとうございました。
インタビューを終えて─
インタビュー中、ひとりのインドネシア人留学生が科目登録の承認サインをもらいに中村先生の研究室に入ってきた。先生はサインをするだけではなく、履修科目を丁寧にチェックしながらアドバイスを与えた上でサインをしていたが、一人一人の学生の個性や考えを尊重しつつ教育プログラムを運営する手際は、とても普通の研究者が及ぶところではないと悟った。その手腕を傍で見る限り、よく言われる大学教員は研究か、教育かという単純な二分法ではJLCの仕事は語れないと感じた。