
このページでは1ヶ月に1回、当センターの教員へのインタビューや、センターが研究・開発中のプロジェクトに関する情報提供を通じて、国内最大の留学生教育機関であるJLCTUFSの「いま」を伝えていきます。
第6回は1年コース・大学院ご担当の楠本徹也准教授へのインタビューです。
自分がどう教えたいかより、学習者は何を学びたいか知ろう
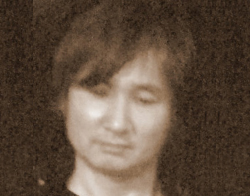
インタビュアー(=Q):今日はお忙しいところ、ありがとうございます。最初に、故郷と少年時代のご自身を教えていただけますか。
楠本徹也教授(=A):生まれは北海道です。札幌で、高校卒業までいました。僕は一人っ子で、ごく普通の子どもだったのですが、小学校6年の時に父親が…彼は進駐軍の仕事をしたこともあったのですが…、まあ彼がリンガフォンのレコードを買ってくれて、それで英語が好きになり、高校までずっと好きでした。大学(青山学院)で英文科に進んだのも、それが理由ですね。
Q:ありがとうございます。では東京に出てからのことを教えていただけますか。
A:青学ではフォークサークルに入りました。サザンオールスターズの桑田佳祐や原由子もいた名門サークルで、そこでフォークをやり、ロックに転じました。よくある音楽青年のパターンです(笑)。卒業後はいったんサラリーマンになったのですが、些細なことで知り合った会社の役員が西イリノイ大学の名誉教授をしていたこともあり、その知遇もあって、留学することにしました。
Q:アメリカにいらしたのですね。
A:そうです。イリノイでは英文学をやったのですが、言語学や言語教育を勉強したかったので、1年後に名門ミシガン大学のアン・アーバー校に転学しました。
Q:それが日本語教育のきっかけですか。
A:その時点では、帰国して大学で英語の教員をしたかったんです。ところがミシガンで名柄先生(元上智大学教授)にお会いしてから、日本語学にも興味が出てきたんです。それから先生の紹介でノースカロライナ州立大学、同じ州内のデューク大学、それからコーネル大学で教えました。アメリカには9年半いたことになりますね。
Q:それから本学へいらしたわけですね。
A:そうです。REXをやり、長春へ行き、6ヶ月コースをやり、1年コースで教え、とセンターの教育プログラムにはほとんど関わりました。
Q:なるほど。ところで先生の、現在の研究のご関心はどのあたりにあるのですか。
A:研究は文法を中心にやってきましたが、今現在となると、教材の開発ですね。最近、「新概念日語」という教科書を中国で出版したんですが、認知的な視点、つまり人間がどういう気持ちで言語を使っているかに着目して開発した教材です。あちらの先生方と共同開発している最中ですが、全部刊行されると18冊になります。この考え方は、コーネルで僕が大きく影響を受けたエレノア・ジョーデン先生に基づくものです。ジョーデン・メソッドというとオーディオ・リンガルか、と思われそうですが、実際はジョーデン先生は文化や発想の相違に基づいた、本当のコミュニケーション能力育成を志向し、それを教材開発にまとめ上げた先生です。僕はその考え方を中国での教材開発に活かしたいと思っています。
Q:ありがとうございました。最後に、これから日本語教育を志す人に対して、何かアドバイスがありましたら、お願いします。
A:今は僕らの頃と違って、いろいろな情報があって便利だと思いますが、ひとつ分からないことは、学生の目線・学生の気持ちで考えろということです。自分がどう教えたいか、ではなくて、学生が何を学びたいか、どう学びたいかを考えれば、教えるべき内容や方法はおのずと見えてくるはずです。そのためにはどんどん、現場で経験を積むことが必要だと思います。
インタビューを終えて─
楠本先生はゼミ生の間では面倒見がよいことで知られている。実際に中国での人脈を活かして実習に連れて行ったり、教材開発を院生と共同でおこなったりと、院生を教師の卵、研究者の卵と位置づけて、単に講義やゼミを行うだけでなく、この世界で長くやっていくためには彼らに何が必要かまで含めて接しているようだ。長い滞米経験、深い中国との関係で築き上げた人脈は、先生自身や研究室のみならず、JLC全体の財産といえるだろう。