
このページでは1ヶ月に1回、当センターの教員へのインタビューや、センターが研究・開発中のプロジェクトに関する情報提供を通じて、国内最大の留学生教育機関であるJLCTUFSの「いま」を伝えていきます。
第4回は1年コースの担当者である工藤嘉名子准教授へのインタビューです。
「国境」は教員を勉強させる教科書です
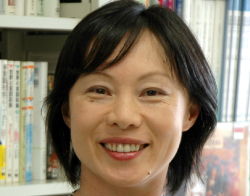
インタビュアー(=Q):今日はお忙しいところ、ありがとうございます。はじめに、小学校から高校までのご自身についてお話いただけますか。
工藤准教授(=A):生まれは青森の八戸で、ICU(国際基督教大学)に進学するまでそこで育ちました。父が英語の教員をしていたこともあり、小学校4年からNHKラジオの英語番組を聴いていました。そのせいか、ずっと英語が好きでした。中学では英語部で英語劇をやっていましたが、演劇が好きになり、高校では演劇部に入って演劇をやっていました。
Q:早くから英語の「音」に触れたことと、今のお仕事と何か関連はありますか。
A:そうですね、たとえば文法から積み上げない外国語の学び方とか、いわゆるチャンク(注:意味を持つ音声の塊)の感覚とかを知ったことは関連があるかもしれません。まあ、こじつけみたいですけど(笑)。
Q:じゃあ、ICUで日本語教育を目指したわけですね。
A:そうです。英語が好きで入学したんですが、バイリンガルの環境に身をおくうちに自分の母語である日本語にも興味が出てきて、言語学や日本語学を勉強し始めました。学部の2年のときには、将来は日本語教育の道に進もうと決めていました。
Q:日本語教師としてのデビューはいつなんですか。
A:修士の2年のとき、カナダのアルバータ州立大学で1年教えてみないか、という話があって教えたのが最初です。それから秋田の旧ミネソタ州立大学機構秋田校、立命館大学、早稲田大学と、任期付きのポジションで仕事をする機会に恵まれました。
Q:さて、工藤先生といえば、教科書『国境を越えて』の分担執筆をされ、このセンターでもお使いになっているということで、そのお話を伺いたいのですが、そもそもの作成に携わったきっかけはどういったことだったのですか。
A:私が執筆に関わったのは、初版本のほんの一部だけです。「国境」は山本富美子先生(現・武蔵野大学大学院教授)のご著書なんですが、立命館大学に勤めていたときに山本先生にお声をかけていただき、一緒にお仕事をさせていただくことができました。「国境」の企画は山本先生が10年来あたためていらっしゃったものでした。3月3日に「桃の会」というグループを立ち上げて、「国境」の作成をはじめたという懐かしい記憶があります。
Q:最初の執筆者のお一人として、この教材をどう評価していますか。
A:『国境を越えて』は、社会科学系の専門教材に区分されていると思うんですが、社会科学系のコンテンツとアカデミック・タスクとを融合させた画期的な教材だと思っています。教科書のコンテンツについて調べたり考えたりしたことを、討論会や調査研究、レポートなどのタスクで表現していくのに必要な材料とプロセスが、教材の中に明確に示されていると思います。同時に、学習者自身が問題提起し、それについて議論したいという気持ちにさせる、そんな刺激的な内容の教科書だと思っています。その意味では、教師も常に問題意識を持って勉強しつづけなければならないので、何年経っても気が抜けない、奥の深い教材です。
Q:そうですか。では今現在は、どういった分野に関心をお持ちなんですか。
A:アカデミック・ジャパニーズ教育全般に関心があるんですが、今は、主に、アカデミック・プレゼンテーションの教材開発とその実践研究に取り組んでいます。内容に深みのあるプレゼンテーションには、学術的な知識と思考力、表現力が必要だと思うんですが、コンテンツとタスクを有機的に結びつけることで、そうしたプレゼンテーションが実現できるのではないかと考えています。
Q:ありがとうございました。それでは最後に、これから日本語教育を志す方や、日本語教育の道に入ったばかりの方に向けて、メッセージをお願いいたします。
A:そうですね…私が日頃の実践で大切にしているのは、今、目の前にいる学習者にとって「意味のある」学びの文脈をどう作るかということです。プレゼンテーション一つをとっても、今なぜこの課題をやるのか、この課題を達成するために自分は何をしなければならないのか、といったことを学習者自身が授業の文脈の中で理解し、積極的かつ自律的にその課題に取り組めるような授業設計を心がけています。ただ、頭で考えた通りに実践が運ばないことも多いので、そういうときには、なぜうまくいかなかったのかを、その都度データに基づき、分析・解明していく必要があると思います。メッセージというよりは自分自身に言い聞かせていることなのですが、実践を批判的に振り返る姿勢、これを常に持ち続けたいと思っています。
インタビューを終えて─
工藤先生は、つねにご自身に与えられた場でベストを尽くすことに賭けてきたようだ。JLCで教える以上、アカデミック・ジャパニーズという視点はすべての教員が有している。しかしそれを教材で体現し、授業で実際にそれを用いて、明確な方法論で実践している点では、やはり工藤先生は屈指の存在である。学習者は授業という状況に能動的に関わらなければならないが、それを可能にしているのは工藤先生ご自身がいちばん積極的に授業のテーマと学習者のそれぞれにダイナミックに関わろうとしているからだろう。